はじめてのカメレオン飼育4|餌の種類と餌やり方法編
- 2024.06.25
- くらしの爬虫類

今回は、カメレオンの餌やりについての記事を書きたいと思います。
我が家で与えているカメレオンの餌の種類とやり方、餌たちの管理環境も書いていきたいと思います。
カメレオンに与える餌の種類
ヨーロッパイエコオロギ

まず一番メインで与えることになるのがこのヨーロッパイエコオロギ(イエコ)。
カメレオンが販売されているお店ならだいたい取り扱いがあると思います、最近はホームセンターのペットコーナーでも売られていてとても便利です。
私はいつもインターネットで購入しています、ショップによるかもしれませんが、寒い時期や地域の場合はカイロを入れてくれていたり、死着保証でプラス何パーセントか増量などのサービスをしてくれます。
我が家のカメレオンは、生まれた時からイエコで育ったからか、一番食いつきがよく入れたらすぐに食べてしまいます。
生後一年くらいは1日5匹くらい。これは、カメレオンを購入した「エイトビート」さんで教えてもらいましたが、5匹は食べさせる量を絞った数で、10匹くらいは食べさせても問題ないそうです。
イエコのデメリットは、オス成体はすごい鳴くのでうるさいこと。
メスはお尻に卵管(画像左下のコオロギはメス)があり見分けが簡単なので、オスから先に与えるようにしています。
フタホシコオロギ

こちらもたまに与えるフタホシコオロギ。
ヨーロッパイエコオロギに比べて色が黒く、動きがにぶいです。
我が家のカメレオンだけかもしれませんが、イエコオロギに比べてめちゃくちゃ食いつきが悪いです。
美味しくないのか、生後一年間はイエコオロギだけで育ったせいかもしれませんが、とにかく食べるまで時間がかかります。
メリットは、イエコに比べて静かなこと。
デュビア
本当は飼いたくなかったのですが、カメレオンをお迎えして3日ほど餌を食べないことがあり、デュビアなら食べるかな、とお試しで30匹だけ買ったもの。
羽がないだけでゴキブリですが、動きも鈍く飛ばないのでだいぶ嫌悪感はありません。
飼育も容易で、たまにキャベツやレタスなどの切れ端とか、ウサギの餌なんかを潰してあげるともりもり食べています。
そしてはじめ30匹だけでしたが、いま数え切れないくらいに増えています。
カメレオン1匹では生涯消費し切れないくらいです、コスパは最強の餌ですが、美味しくないのかカメレオンの食いつきはあまり良くないです。

たまのおやつ感覚であげています。
でかいやつは気持ち悪くなってくるのでなるべくでかいのから消費していっています。
ミルワーム

魚の餌としても売られているミルワーム、カメレオンも結構食べます。
こちらもホームセンターに安価で売られています。
なるべく大きいものから与えていくと成虫になるのを防げますが、成虫は成虫でありがたいことがありました。

入れ物は小さいので百均で売られているケースに入れ替えて管理しています。
こちらもおやつ感覚であげます、栄養はないらしいので。
ダスティングとガットローティング
ちなみに全ての餌にはカルシウム+ビタミン剤をふりかけています。
イエコにはカルシウムが少ないので、これをイエコにふりかけて食べさせることで手軽にカルシウムを摂らせるという方法です。
これを「ダスティング」と言うそうです。
イエコやデュビア自身の餌を栄養価の高いものにして、それをカメレオンに与えることを「ガットローティング」と言うそうです。

ただ体の小さな生体にビタミンを与えすぎるのも良くないようで、毎回ふりかけるのではなく、たまにふりかけて与える程度でいいようです。
このダスティングとガットローティングなんて言葉は、カメレオンを飼うまで知りませんでした、勉強になるなぁ。
餌入れの置き場所作り
餌はカップに入れて与えています。

百均のカップにキンカチョウのつぼ巣用の引っ掛けがちょうどよかったのでこれを使っています。

赤はちょっとあれなので黒く塗装しました。

チェーンをカメレオンのケージの端の方の上に設置。

そこにカップを置いたら餌置き場の完成です。

イエコを入れて置いておいたらカメレオンが好きなタイミングで食べてくれます。

お腹が空いていたらすすすーっとよってきて舌を伸ばします。
時間があるときは、カップを手で持って与えてます。
時間はかかりますが、すごい警戒しながらちょっとずつ寄ってきて、舌を伸ばしてくれたらなんか嬉しい気持ちになります。
餌たちの管理環境
コオロギの環境
コオロギの飼育環境はこんな感じです。

初めはただ水槽に入れて編みをして管理していました。
100匹を飼い、毎日5匹与えていたら20日は持つはずなんですが、だいたい10日以内に全滅してしまいます。
床材を入れる

水槽を小さく、百均で買ったヤシガラの床材をいれ、パネルヒーターで保温をしました。


卵ケースはかなり優秀でこれは水槽に入るだけ入れてもいいと思います。
隠れ家になって、水槽が小さくてもたくさんのイエコを管理できるようになります。
床材と保温で死ぬ数は段違いで減りましたが、しばらくして気づきました。
なんか臭い…。
床材を変える
保温と湿度で蒸れて、触ってみるとヤシガラがかなりしっとりしてしまっているので、これが臭い(おそらくカビ)の原因かと思います。
床材をヤシガラから赤玉土に変えてしばらく様子見。
しかしやはり少しするとニオってきました。
どうしたものか。
やっぱり床材をなくす

そうこうしているうちに夏が来たので、パネルヒーターを撤去、それに合わせて床材もなくして卵ケースだけで管理することにしました。
卵ケースがもうボロボロだったので全部捨てたてなので少ないですが、10個くらいを積み上げています。
ありったけの卵ケースを入れて、また冬がきたらヒーターでどんな感じになるか試してみたいと思います。
コオロギの餌は、昆虫ゼリー、野菜のいらないところ、レオパのフードをすりつぶしたものを与えています。
水飲み場
コオロギは当然、水がないと死んでしまうので水槽内にも水飲み場が必要です。
しかし水があると蒸れの原因と溺死もあるので結構管理が大変。
我が家では綿棒の空ケースの蓋に穴を開けて中に水を入れ、キッチンペーパーを差し込んで水を吸い上げるようにしています。

これなら溺死はしないし必要以上に水が放出されることもありません。
水飲み場改変
数ヶ月使いましたがちょっと高さがありすぎて、小さめのコオロギにはたどり着けないこともあったので、改良することにしました。

この器にスポンジを切って入れ、

水を定期的に染み込ませて与えます。
水を入れるとスポンジが濃くなるので乾燥しだしたらわかります。
デュビアの環境
透明の水槽で管理していましたが、見た目がやっぱりアレなのでちょっと改良。

あまり散らかしていた百均のケース、蓋に穴を開けてここで管理します。
ついでに廃材を使ってこのケースを収納する棚を作成。
デュビア棚を製作

板を切って、

四角くビスで止めます。

細かい板を作って、

細かい板をこう設置。

そこに使っていなかったイケアの網棚を使います。

それを板で作った溝に差し込んで棚の完成。
そこに百均のケースを置いていって、

デュビア入れの完成です。
サイズ別にデュビアを管理しようと思ったんですが、結局でかいデュビア、生まれたてのデュビアにしか分けてないので、使わない他のケースはただの物入れになっています。
そしてしばらくしてちょっとケースの色が気に入らなかったので、

色を変えてシックな感じに。
まさかここに大量のデュビアが入っているとは思わないでしょう。

こちらも卵ケースを入れています。
卵ケースをどうやら食べるようなのですが、卵ケースを食べだしたら餌が枯渇しているサインなのでもっと高頻度であげないといけません。
1週間に一度は餌を新しくするサイクルでやっています。
ミルワームの環境
ミルワームは基本的に買ったままのケースで数ヶ月持ちます。

が、気づくと蛹が増え、やがてこんな甲虫が何匹かできあがりました。
ミルワームがこんな姿になるとは驚きですが、まぁ特に害もないのでこのまま放置していたら、たくさんのミルワームの子供がいることに気づきました。
デュビアよりも時間がかかりますが、ミルワームも簡単に増やすことができるとは知りませんでした。

なので15センチキューブ水槽に土とおがくずを入れてもっと増えるように改良。
たくさん増えたらいいな。
まとめ
我が家のカメレオンは、
ヨーロッパイエコオロギ→ミルワーム→フタホシコオロギ→デュビア
の順番で好きな様子。
イエコのメリットは食いつきがいい、デメリットはうるさい。
ミルワームのメリットは食いつきが良く管理も楽、デメリットは栄養がない。
フタホシコオロギのメリットは静か、デメリットは美味しくない。
デュビアのメリットは管理が楽で勝手に増える、デメリットは美味しくない。
爬虫類の餌はなんだかとても奥が深くてまだまだ勉強不足だと感じます。
カメレオンがもっといい環境で過ごせるように精進したい。
くらしをあげる、kuranでした。
◼︎イエコが増えたら嬉しいけど難しい◼︎
-
前の記事

こどもとお出かけ|滋賀【ザキッズ草津店】広い屋内施設で充実の遊具 2024.06.23
-
次の記事

子どもとお出かけ|兵庫【竹野浜海水浴場】高い透明度と温泉が嬉しい 2024.08.20










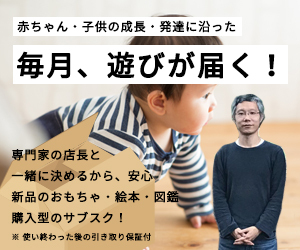




















コメントを書く